「愛犬がウンチを食べちゃう…」と困っている飼い主さんは多いのではないでしょうか。実は、野生の犬や狼でも食糞はよくある行動。でも、放置は厳禁!病気や寄生虫感染のリスクがあるからです。
この記事では、食糞の原因と対処法をわかりやすく解説します。愛犬の健康を守るため、ぜひご一読ください!
犬が食糞する理由とは?

犬の食糞は、飼い主にとって悩ましい問題です。犬が自分の糞や他の犬の糞を食べるのには、さまざまな原因があります。
食事に問題がある場合
犬の食糞は、様々な原因で起こる可能性があります。
その中でも、食事内容に関連する理由は多く見られます。
- 食餌量の不足:犬が空腹を感じると、便に含まれる栄養分を摂取しようと食糞を行う場合があります。
- 栄養バランスの偏り:栄養バランスが偏った食事は、消化不良を引き起こし、便に栄養が残る可能性があります。これが食糞を誘発することもあります。
- 消化不良を起こしやすい食事:消化不良を起こしやすい食事は、便が未消化のまま排出されるため、食糞を誘発しやすくなります。
病気による空腹感の増加
愛犬が空腹感を訴えたり、便を食べようとしたりする場合は、病気が潜んでいる可能性があります。
消化器系の病気、内分泌系の病気、代謝性疾患など、空腹感を増す病気がいくつか存在します。
愛犬の健康状態が気になる場合は、早めに獣医師の診察を受けることをおすすめします。
精神的要因
食糞は、単なる不衛生な行為ではなく、犬の健康や精神状態に何らかの問題があるサインである可能性があります。
ストレスや不安、退屈さなどが原因となって、食糞をする場合があります。
ストレスの原因となるものを取り除く、留守番の時間を短くする、他の犬との接触を避ける、十分な運動と遊びを提供する、噛むおもちゃなどを与えて退屈さを解消するなど、犬のストレスや不安を取り除き、十分な運動と刺激を与えることが大切です。
母性行動による理由
母犬が子犬の排泄物を食べる本能的な行動が成犬になっても残ってしまう場合や、子犬が母犬の真似をして食糞をする場合があります。
子犬の食糞は成長とともに自然に治ることが多いですが、成犬になっても続く場合は他の原因も考えられるため注意が必要です。
子犬の食糞は原因が異なる?

子犬の食糞は、成犬よりも頻繁に見られる行動です。これは、子犬はまだ消化器官が未熟で、必要な栄養素を十分に吸収できていないため、便に栄養が残っていることが原因と考えられます。
また、好奇心旺盛な子犬は、何でも口に入れてしまうため、誤って便を食べてしまうこともあります。
子犬の食糞は以下の理由によって起こることもあります。
- 食事不足:子犬は成長期のため、多くのエネルギーを必要とします。食事量が足りていないと、空腹感から便を食べてしまうことがあります。
- 食事内容:子犬に与えているフードが栄養バランスに欠けていたり、消化が悪い場合も、食糞を引き起こす可能性があります。
- ストレス:子犬は、環境の変化や分離不安などによってストレスを感じると、食糞をすることがあります。
- 寄生虫: 寄生虫に感染している子犬は、栄養不足や消化不良を起こし、食糞をすることがあります。
子犬の食糞は、病気のリスクにつながるため、早急にやめさせる必要があります。
食糞をやめさせるためには、以下の方法が有効です。
- 食事量の調整:子犬の成長に合わせて、適切な量のフードを与えるようにしましょう。
- フードの変更:消化の良い、栄養バランスのとれたフードに切り替えるようにしましょう。
- ストレスの軽減:子犬のストレスを軽減するため、十分な運動と休息を与え、環境を落ち着かせるようにしましょう。
- 寄生虫の駆除:定期的に動物病院で寄生虫の検査を行い、必要に応じて駆除するようにしましょう。
子犬の食糞は、成犬に比べて原因が異なる場合が多いため、適切な対策を講じて早期にやめさせることが大切です。
食糞をやめさせるべき?病気のリスクは?

食糞は、犬の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。原因を特定し、適切な対策をとることで、食糞をやめさせることができます。
特に注意すべき犬
子犬
- 消化器官が未発達なため、栄養素の吸収が十分でない。
- 空腹感を感じやすく、食糞をすることがある。
- 好奇心旺盛で、何でも口に入れてしまうため、誤って便を食べてしまうこともある。
高齢犬
- 消化器官の働きが衰え、便秘を起こしやすくなる。
- 便秘になると、硬い便が腸に残り、排便が困難になる。
- 排便を促そうとして、便を食べてしまうことがある。
特定の疾患を持つ犬
- 腸の病気や消化器系の病気など、特定の疾患を持つ犬は、消化不良を起こしやすく、空腹感を感じやすくなる。
- 精神的な問題を抱えている犬も、ストレス解消のために食糞をすることがある。
これらの年齢や特徴に当てはまる犬は、食糞の原因を特定し、適切な対策を講じることが重要です。獣医師に相談し、必要に応じて検査や治療を受けるようにしましょう。
同居する他の動物の排便について
同居している動物の排泄物が犬にとって魅力的に感じることも食糞の原因になります。 特に猫は砂場を好むため、排泄物を隠しきれずに残ってしまうことが多いため注意が必要です。 猫のトイレはこまめに掃除をしたり、犬が近づけない場所に設置するなどの工夫をしましょう。 また、他のペットが排泄した直後の場所には近づけないように、リードなどで行動範囲を制限するなど、対策が必要です。
外出先での食糞
食糞は公園や散歩道など、公共の場で発生すると、衛生面や他の人の不快感を招く恐れがあります。
- 他の犬の糞が混ざっている:公園や散歩道には、他の犬の糞が放置されていることが多く、それが食糞を誘発する可能性があります。
- 好奇心から:特に子犬は、好奇心旺盛で、様々なものを口に入れてしまいます。糞もその一つであり、興味本位で食べてしまうことがあります。
- 栄養不足:栄養バランスが崩れた食事をしていると、犬は空腹感を覚え、糞に含まれる栄養分を求めて食べてしまうことがあります。
- ストレス:ストレスを感じている犬は、不安を解消するために食糞をすることがあります。
外での食糞を防ぐためには、以下の対策が有効です。
- 犬の糞を放置しない:散歩中に犬が排便したら、必ず飼い主が責任を持って糞を回収しましょう。
- 犬をリードで繋ぐ:犬が他の犬の糞に近づけないように、リードで繋いでおくことが重要です。
- 食事内容を見直す:栄養バランスの取れた食事を与えることで、空腹感を抑えることができます。
- ストレス解消に努める:散歩や遊びなど、犬がストレス解消できる時間を設けましょう。
- 食糞防止剤を使用する:食糞防止剤は、犬が嫌がる味や匂いで糞を食べないようにする効果があります。
- しつけを行う:食糞をしたら、叱らずに「ダメ!」と注意し、別の行動に切り替えさせましょう。
これらの対策を組み合わせることで、外での食糞を防ぐことができます。
食糞対策はどうすればいい?

体調の変化を見逃さない
犬が食糞をする原因として、体調不良が考えられる場合もあります。 以下のような症状が見られる場合は、動物病院で診察を受けることをおすすめします。
- 食欲不振
- 嘔吐
- 下痢
- 元気がない
- 体重減少
- 便に血が混じっている
- 便が軟らかい
- 便が硬い
これらの症状は、消化器系の病気や寄生虫感染などの病気が原因となっている可能性があります。食糞だけでなく、他の異常も見られる場合は、早めの受診を心がけましょう。
食事を見直しましょう
食事量を再計算する
フードを変える
フードの変更は、食糞の原因がフードにある場合に有効な対策です。
消化の良いフード、高タンパク質・低繊維のフード、グレインフリーのフードを選ぶことで、便の臭いを軽減し、食糞をする意欲を下げることができます。
フードを変更する場合は、獣医師に相談して適切なフードを選び、徐々に新しいフードに切り替えることが大切です。
犬がウンチを食べるのは、空腹だったり、食事内容に問題があったり、病気だったり、精神的なストレスを感じていたりすることが原因です。
食事量や食事内容の見直し、病気の早期発見と治療、ストレス対策をすることで、ウンチを食べるのを防ぐことができます。
栄養バランスに優れたおすすめドッグフード
ディアラ 馬肉パーフェクトプラス

“ディアラ 馬肉パーフェクトプラス“は、高品質の馬肉を主原料としたドッグフードです。馬肉は低脂肪で高タンパク質であるため、犬の健康維持に最適です。
実際にディアラの商品をご利用頂いているお客様から「食糞しなくなりました」とお声を頂きました。
ディアラ 馬肉パーフェクト

“ディアラ 馬肉パーフェクト“は、食糞に悩む犬のために開発された高品質なドッグフードです。高タンパク質、低脂質の馬肉を主原料としており、栄養バランスに優れています。
ディアラの商品を実際に使用しているお客様の声
30代 女性
食フンをしなくなりました。今まで手作り食でしたが、食フンが酷く悩んでいました。
憧れだったディアラさんに思い切って換えたところ、ピタリと止みました!
栄養がしっかり取れている証だと思います。
おいしくてたまらないのか、用意している時にキャンキャン催促される事だけが悩みです笑
ストレスの発散方法
犬の食糞をやめさせるには、発散不足を解消することが大切です。犬は本来、狩猟本能を持っているため、運動不足になるとストレスが溜まり、そのストレス解消のために食糞をしてしまうことがあります。
発散不足を解消するための対策
- 毎日散歩をさせましょう。散歩中に走る、ボール遊びをするなど、身体を思いっきり動かすことができれば、ストレス解消に効果的です。
- 天候が悪い時や、時間がない時は、室内でボール遊びや引っ張りっこなどの遊びをしましょう。
- ドッグランは、他の犬と遊んだり、走り回ったりできる場所です。犬の社会化やストレス解消にも効果的です。
- 犬のトレーニングは、集中力と体力を使うため、発散不足解消に効果的です。また、飼い主との絆も深まります。
【まとめ】愛犬の食糞は止められる

食糞は、適切な対策をとることで、やめさせることができます。
愛犬の健康を守るためにも、食糞の原因を理解し、適切な対策をとりましょう。
監修・運営者情報
| 監修・運営者 | 株式会社ディアラ |
| お問い合わせ | tel: 046-836-0829 e-mail: petfoodfactory@diara-plus.com |
| WEBサイト | https://petfoodfactory.diara-plus.com/ |








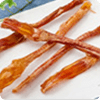



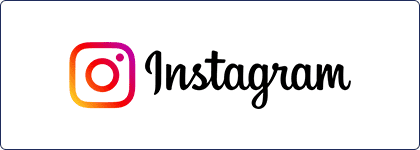
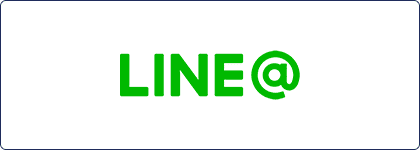




コメント